錦鯉の飼育が難しい3つの理由とよくある失敗例を紹介
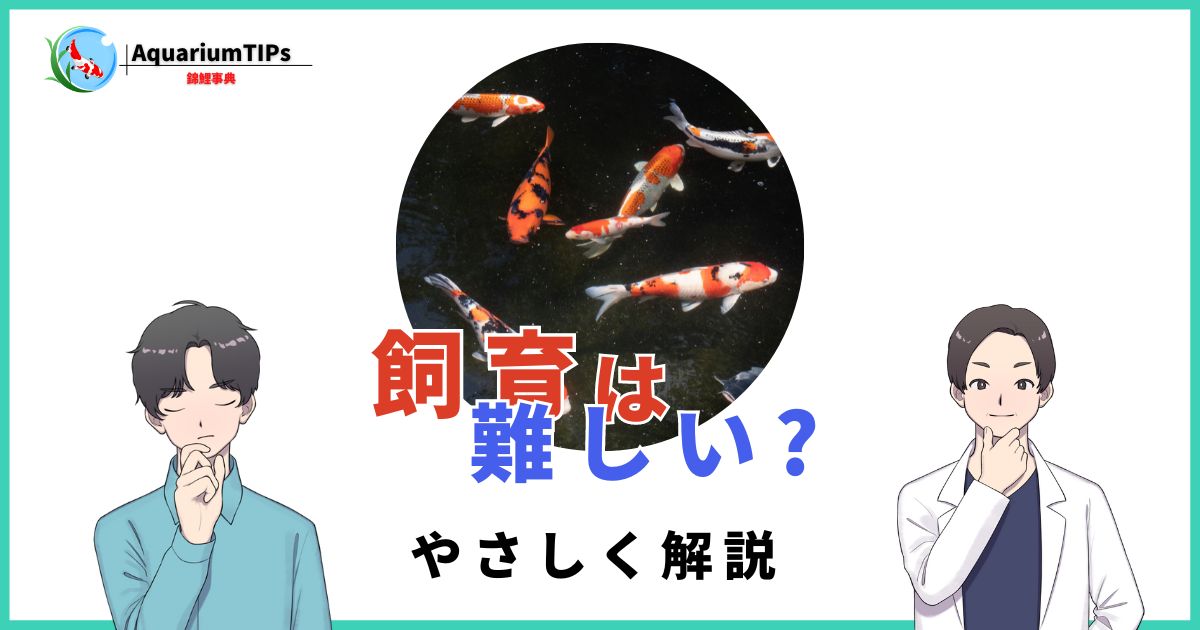
錦鯉はメダカや金魚、小さな熱帯魚と比べてサイズがはるかに大きいことから飼育が難しいと思われがちです。しかし、実際はどんな魚も飼育のルールは変わりありません。
錦鯉の大きさや飼育数に合わせた適切なサイズの水槽や池の選定、水換えの頻度や水を入れるときの水温や水質、餌を与える量を守ることができれば安定して飼育を楽しむことができます。
この記事では錦鯉飼育で難しいと言われる代表的な理由とよくある飼育の失敗事例をまとめているのでポイントごとの注意点をこれからの飼育参考にしてみてください。
錦鯉の飼育が難しいと言われる3つの理由
1.水質管理と水温調整が難しい
錦鯉の飼育で最も難しいと言われるのが、水質管理と水温調整です。
錦鯉は水質の変化に敏感で、アンモニアや硝酸塩などの有害物質が溜まると健康を害します。
水槽のサイズと飼育数、錦鯉のサイズに合わせた適切な水量、といった飼育に適した条件を確保できていない環境下で水質悪化するとアンモニア中毒によって急死してしまうこともあります。
また、急激な水温の変化にも弱いため、季節ごとの適切な水温管理が必要です。
例えば、夏場は25℃前後、冬場は10℃前後が理想的です。これらの管理を怠ると、錦鯉がストレスを感じたり、病気にかかりやすくなったりします。そのため、定期的な水質検査や水温計の設置、そして状況に応じた対策が欠かせません。

慣れるまでは大変かもしれませんが、慣れれば楽勝!
2.水量の確保が大変


錦鯉の健康的な成長には、適切な飼育環境の整備が不可欠です。
一般的に、錦鯉1匹につき最低でも100リットルの水が必要だと言われています。また、食べ残しや糞などの汚れをしっかりと除ける濾過フィルターの導入も重要です。
さらに、錦鯉は酸素を多く必要とするため、エアレーションの設置も欠かせません。水槽サイズや水槽にあった濾過フィルターを選び、設置・維持することは、特に初心者にとっては難しく感じられるかもしれません。



飼育用具はケチって小さいサイズなどにしない方が良いです
3.病気対策が難しい


錦鯉の飼育で避けて通れないのが、病気対策と健康管理です。
錦鯉は様々な病気にかかりやすく、特に水質の悪化や急激な環境変化によってストレスを受けると、病気にかかるリスクが高まります。代表的な病気には、白点病、鰓腐れ、水カビ病、寄生虫による感染などがあります。
これらの病気を予防するには、日常的な観察と適切な対策が必要です。例えば、定期的な塩水浴を行うことで、寄生虫の予防や体表の粘膜保護ができます。また、錦鯉の行動や外見の変化に注意を払い、異常を早期に発見することも重要です。病気になってしまった場合は、同じ症状の改善方法をネットで探してみたり、購入したお店・ブリーダーに相談したり、適切な薬を使用したりする必要があります。
持っていて安心の魚病薬
錦鯉飼育を簡単にする3つのポイント
飼育用品はケチらない
錦鯉の飼育を簡単にするなら、飼育用品はケチらない方が良いです。
例えば、60cm水槽と90cm水槽では値段が大きく異なります。また、それらの水槽サイズに合わせたフィルターやクーラー、ヒーターなども購入することを考えると大きなサイズになる程、必要な用具は高くなります。
水槽が小さかったり、フィルターが小さいと水質管理が難しくなり、結果として錦鯉のストレスになります。初心者であっても水槽のサイズは大きい方が飼育のトラブルは少ないです。。
また、濾過フィルターやエアレーション、ヒーター、クーラーについてもケチらず、飼育水槽のサイズにぴったりなものを選ぶようにしましょう。


濾過フィルターを導入する
濾過フィルターは水槽内の水をきれいに保てるので導入は必須です。初心者におすすめなのは、上部式フィルターです。これは水槽の上に設置するタイプで、使い方が簡単で効果も高いです。
上部フィルターには以下の3層構造がおすすめです。
| 下層 | バクテリアの住処となる多孔質な濾材 |
|---|---|
| 中層 | 活性炭(水の汚れを吸着) |
| 上層 | ウールマット(目に見える汚れを取り除く) |



上部フィルター用バクテリアマットプラスで大体解決できるよ
濾材の洗浄は上2層だけにとどめ、下層はなるべく洗わないようにしましょう。多孔質な素材はバクテリアが定着するので洗ってしまうと濾過システムが崩れたり、かえって水質悪化を招くことがあります。
与える餌の量を覚える
錦鯉への正しい給餌は錦鯉の体力向上や免疫力の強化、病気の対策、水質良好の維持につながります。基本的な餌やりの目安は、5分〜10分で食べきれる量を1日1回与えることです。ただし、季節によって錦鯉の活動量は変化します。
季節ごとの餌やり目安
| 季節 | 水温 | 給餌頻度 |
|---|---|---|
| 春・秋 | 15-20℃ | 1日1回 |
| 夏 | 20℃以上 | 1日2~3回 |
| 冬 | 10℃以下 | 3~7日に1回または給餌停止 |
エサの種類も重要で、市販の錦鯉用フードを基本としつつ、季節に応じて色揚げ用や低水温用のエサを使い分けると良いでしょう。与えすぎは水質悪化の原因になるので注意が必要です。
難しい要因?錦鯉飼育によくある失敗
餌のやりすぎ
錦鯉飼育で最もよくある失敗の一つが餌のやりすぎです。錦鯉は食欲旺盛で、エサをあげると常に食べる姿勢を見せるため、つい与えすぎてしまいがちです。しかし、これは非常に危険です。
餌のやりすぎるデメリット
- 水質の急激な悪化
- 錦鯉の肥満や内臓疾患
- 餌の食べ残しによる水槽底の汚れ
- アンモニア濃度の上昇
先述したように餌は5分以内に食べきれる量を1日1程度与えるのが理想的です。また、錦鯉の体型をよく観察し、お腹が膨らんでいたら給餌量を減らすなどの調整も必要です。休日に備えてまとめて与えるのも避けましょう。
水の変え過ぎ・大量の水換え
水替えは錦鯉の健康維持に不可欠ですが、不適切な方法で行うとストレスの原因になります。よくある失敗として、大量の水を一度に交換したり、水換え頻度が多すぎること、水温や水質の大きく異なる水を入れたりすることが挙げられます。
正しい水換えのポイント
- 週に1回、水量の25〜30%程度を交換する
- 新しい水は必ずカルキ抜きをする
- 水温を現在の水槽の水とほぼ同じにする
- ゆっくりと少しずつ水を足す
また、水替え時は錦鯉をネットですくい上げず、水槽内に置いたままにしましょう。これにより、錦鯉への物理的なストレスを軽減できます。定期的かつ適切な水替えは、錦鯉の健康と美しさを保つ上で非常に重要です。
購入後の水合わせの失敗
錦鯉は丈夫な魚ですが、環境の急激な変化に非常に弱い生き物です。
特に水温、pH、硬度などの急激な変化は、錦鯉に大きなストレスを与え、最悪の場合死亡につながることもあります。よくある失敗例として、新しい錦鯉を購入した際にすぐに水槽に入れてしまうことが挙げられます。



購入時は、焦る気持ちを抑えて水合わせをゆっくり行うようにしましょう
- 購入した袋ごと水槽に浮かべ、30分ほど水温を合わせる
- 袋の水と水槽の水を少しずつ混ぜる(15分ごとに)
- 1時間ほどかけて徐々に水槽の水に慣れさせる
- 最後に錦鯉だけを静かに水槽に移す
また、季節の変わり目など、環境が変化しやすい時期には白点病や尾ぐされ病が発症する確率が高くなります。水温の管理や、適切な餌の選択など、季節に応じたケアを心がけましょう。










